【基礎】ダイレクトパーツマーキングとは?基礎から詳しく解説!
製造現場での個体管理、どうしていますか?ラベル貼りでは剥がれてしまう、過酷な環境で使えない、といった課題を抱えているなら「ダイレクトパーツマーキング(DPM)」が解決策になるかもしれません。部品そのものに直接マーキングするため、耐久性に優れ、確実なトレーサビリティを実現します。本記事でDPMの基本を学び、自社の品質管理と生産性向上に繋げましょう。

目次
ダイレクトパーツマーキング(DPM)とは?
ダイレクトパーツマーキングの基本的な意味
部品に直接印字する技術
ダイレクトパーツマーキング(Direct Parts Marking)とは、その名の通り、製品や部品(パーツ)の表面に直接(ダイレクトに)情報を印字(マーキング)する技術のことです。一般的には、二次元コードや英数字、シリアルナンバーなどを刻印します。この技術の最大の特徴は、対象物自体が情報のキャリアとなる点です。高温、洗浄、摩擦といった過酷な環境でも情報が消えにくく、製品のライフサイクル全体を通じて個体管理や追跡を可能にします。自動車部品や電子部品、医療機器など、高いトレーサビリティが求められる業界で広く活用されています。
ダイレクトマーキングには、用途に合わせてレーザーマーキングやドットピーニングやインクジェット方式などの方法があります。
ラベル貼りとの違い
従来、個体管理には紙やフィルムのラベルを貼り付ける方法が一般的でした。しかしラベル方式には「剥がれ」や「汚れ・摩耗による印字消失」「熱や薬品への耐性の低さ」「貼り付けスペース」といった課題があります。一方、ダイレクトパーツマーキングは、部品そのものにレーザや打刻で刻印するため、これらの問題が発生しません。部品と情報が一体化しているため、半永久的に情報を保持できる高い耐久性を誇ります。また、ラベルを貼るスペースがないような微小な部品にも印字できる点や、ラベルやインクリボンといった消耗品が不要になる点も大きな違いと言えるでしょう。
なぜ今ダイレクトパーツマーキングが注目されるのか?
トレーサビリティ向上の重要性
近年、製造業においてトレーサビリティの確保は極めて重要な経営課題となっています。万が一製品に不具合が発生した場合、いつ、どこで、誰が、どの部品を使って製造したのかを迅速に特定し、影響範囲を最小限に抑える必要があります。ダイレクトパーツマーキングによって部品一つひとつに固有の識別子を付与することで、製造から廃棄までの全工程を追跡可能になります。これによりリコールの迅速化、原因究明の精度向上、そしてブランドイメージの保護に繋がります。規制が厳しい自動車や航空宇宙、医療業界などを中心にその重要性はますます高まっています。
品質管理と生産性向上への貢献
ダイレクトパーツマーキングは、高度な品質管理体制の構築にも貢献します。各工程で部品の情報を正確に読み取ることで、ポカミス(ヒューマンエラー)を防止し、正しい部品が使われているかを自動で照合できます。また、工程ごとの作業実績や検査結果を個々の部品情報と紐づけて記録することで、品質データの精度が飛躍的に向上します。これにより不良品の発生原因を早期に特定し、再発防止策を講じることが可能になります。さらに仕掛品の管理や在庫管理の自動化も促進され、生産性向上にも大きく寄与します。
ダイレクトパーツマーキングの主な印字方式と特徴
レーザマーカ方式
メリット:高精細で耐久性が高い
レーザマーカ方式はレーザ光を対象物に照射し、その熱エネルギーで表面を変化させて印字する方法です。非常に微細で高精細な印字が可能で、小さな二次元コードやロゴマークなども鮮明にマーキングできます。金属の酸化を利用した発色や、樹脂への黒色印字など、材質に応じて最適な印字品質を得られるのが特徴です。また物理的に表面を削るわけではないため素材へのダメージが少なく、印字そのものが摩耗や経年劣化に強いという優れた耐久性を誇ります。非接触で印字できるため、製品の形状に影響されにくい点もメリットの一つです。
デメリット:導入コストと材質の選定
レーザマーカ方式の主なデメリットは、他の方式に比べて初期の導入コストが高額になる傾向がある点です。装置本体が高価であることに加え、安全な運用環境を確保するための集塵機や保護具なども必要になります。また、レーザの種類(ファイバレーザ、CO2レーザなど)によって、印字できる材質との相性が異なります。例えば、CO2レーザは樹脂やガラスには適していますが、多くの金属には印字しにくいといった特性があります。そのため、マーキングしたい対象物の材質を事前にしっかりと見極め、最適なレーザ方式を選定する必要があります。
ドットピーンマーカ方式
メリット:打刻による耐久性とコスト
ドットピーンマーカ方式は、先端が硬い金属でできたペンを振動させ、対象物に押し付けて点(ドット)の集合で文字やコードを刻印する方法です。物理的に打刻するため、非常に深く、耐久性の高いマーキングが可能です。熱や薬品、塗装など後工程の影響を受けにくく、鋳造部品のような凹凸のある表面にも確実に印字できるのが大きな強みです。また、装置の構造が比較的シンプルであるため、レーザマーカ方式に比べて導入コストやランニングコストを低く抑えられる傾向にあります。メンテナンスが容易な点も現場にとっては嬉しいメリットです。
デメリット:印字の細かさと騒音
ドットピーンマーカ方式のデメリットとしては、まず印字品質の細かさに限界がある点が挙げられます。打刻による物理的なマーキングであるため、レーザマーカのような高精細な印字は困難です。非常に小さな二次元コードの印字には向いていません。また、金属にペンを打ち付けて刻印する仕組み上、どうしても大きな打刻音が発生します。作業環境によっては、騒音対策として防音カバーなどを設置する必要があるでしょう。さらに、マーキング時に部品をしっかりと固定する必要がある点も考慮すべきポイントです。
インクジェット方式
メリット:非接触で多様な材質に対応
インクジェット方式は微細なインクの粒子を対象物に直接吹き付けて文字やコードを印字する方法です。最大のメリットは、非接触でマーキングできる点です。これにより製品に物理的なダメージを与えることなく、凹凸のある面や曲面にも容易に印字が可能です。またインクの種類が豊富で、金属、樹脂、ガラス、ゴムなど、さまざまな材質に対応できる汎用性の高さも魅力です。速乾性のインクを使用すれば、高速な生産ラインや物流コンベアと組み合わせて仕分けコード印刷などに組み込むことができ、比較的安価に導入できる点もメリットと言えるでしょう。
デメリット:消耗品と耐久性
インクジェット方式の明確なデメリットは、耐久性の低さと消耗品の存在です。インクを表面に付着させているだけなので、摩擦や洗浄、薬品などによって印字が剥がれたり消えたりする可能性があります。半永久的な管理が求められるトレーサビリティ用途には不向きな場合があります。また、インクや溶剤といった消耗品が継続的に発生するため、ランニングコストがかかります。さらに、ノズルの詰まりなど定期的なメンテナンスが必要不可欠であり、これを怠ると印字品質の低下や装置のトラブルに繋がる可能性があります。
ダイレクトパーツマーキングの読み取りと課題
なぜ専用のコードリーダが必要なのか?
DPMコード特有の課題(低コントラスト、凹凸など)
ダイレクトパーツマーキングで印字された二次元コードは、紙に印刷されたコードとは大きく性質が異なります。例えば、金属に打刻されたコードは背景とのコントラストや精度が非常に低く、光の当て方によってはほとんど見えません。また、レーザで印字した場合でも表面の光沢(ハレーション)や鋳肌のようなザラザラした面、曲面への印字による歪みなど読み取りを阻害する要因が数多く存在します。一般的なコードスキャナは、こうした悪条件下での読み取りを想定して設計されていないため、DPMコードを安定して読み取ることは極めて困難です。
専用リーダの画像処理技術
DPMコードを安定して読み取るためには、専用に設計された二次元コードリーダが不可欠です。これらのリーダは、DPM特有の課題を克服するための高度な技術を備えています。例えば、様々な角度から光を照射する照明技術や特殊光(特定波長)によってハレーションを抑制し、低コントラストなコードでも鮮明に撮像します。さらに、撮像した画像から歪みやノイズを除去し欠損した部分を補完する強力な画像処理アルゴリズムが搭載されています。これにより、どんなに条件の悪いDPMコードでも瞬時に、そして正確にデコードすることが可能になるのです。お問い合わせはこちら。
読み取り精度を上げるためのポイント
最適な印字条件の選定
DPMコードの読み取り精度は「出口」であるリーダの性能だけでなく、「入口」である印字品質に大きく左右されます。読み取りやすいコードを印字することが、安定した運用のための最も重要なポイントです。そのためには、対象物の材質や表面状態に合わせて最適なマーキング方式と印字設定(レーザの出力、打刻の深さ、下処理など)を選定する必要があります。事前にメーカと協力し、十分な印字テストを行うことが不可欠です。セルのサイズや形状、クワイエットゾーン(コードの周囲の余白)の確保など、コードの規格に準拠した印字を徹底することも基本中の基本です。
照明(ライティング)の重要性
DPMコードの読み取りにおいて、照明(ライティング)は極めて重要な要素です。人間の目では同じように見えても、光の当て方一つでコードリーダにとっての「見えやすさ」は劇的に変化します。例えば、光沢のある金属表面には正反射を避けるドーム照明や同軸落射照明が有効です。一方で、打刻された凹凸を強調したい場合は、低い角度から光を当てるローアングル照明が適しています。透明なガラスなどでは、透過光を利用して影を読み取るのも有効です。このように、コードの状態や背景の材質に応じて最適な照明を選定し、組み合わせることが読み取り精度を最大限に引き出すための鍵となります。
まとめ
本記事ではダイレクトパーツマーキング(DPM)について、その基本から応用までを解説しました。DPMは部品に直接情報を刻印することでラベル貼りの課題を克服し、高い耐久性を実現する技術です。トレーサビリティの向上や品質管理の高度化に不可欠であり、レーザ、ドットピーン、インクジェットといった方式から対象物に応じて最適なものを選びます。読み取りには専用のコードリーダが必要ですが、適切な印字と照明が安定運用の鍵となります。この記事がDPMの理解と導入検討の一助となれば幸いです。本コラムでは、今後も皆様のお役に立つ情報の発信を続けてまいります。
投稿者プロフィール
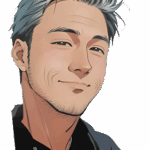
- 業界27年のベテラン営業マン兼ライター。
積極的に海外からも良い製品を探してくるが基本的にはモノづくり大好き人間。





