【業務効率化】バーコードとRFIDの活用事例5選を詳しく解説!
「在庫管理のミスが減らない」「棚卸しに時間がかかりすぎる…」そんなお悩みありませんか?もしかしたら、その課題はバーコードやRFIDで解決できるかもしれません。この記事では、よく似ているようで全く違うバーコードとRFIDの基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、具体的な活用事例までを徹底的に解説します。あなたの会社の業務を劇的に効率化するヒントが、きっと見つかりますよ。

目次
バーコードとRFIDの基本をサクッと理解!
今さら聞けない「バーコード」の仕組み
バーコードの仕組みと読み取り方法
バーコードは、太さの異なる黒い線(バー)と白い線(スペース)を組み合わせた縞模様のことで、このパターンに商品コードなどの情報が格納されています。いわば、コンピュータが読み取れる「文字」のようなものですね。読み取りには、バーコードリーダやスキャナと呼ばれる専用の機器を使います。リーダから照射された光がバーコードに当たり、黒い線は光を吸収し、白い線は反射します。この反射光の強弱を電気信号に変えて、元の情報に変換しているんです。スーパーのレジで「ピッ」とやる、あのお馴染みの光景がまさにこの仕組みですね。手軽に導入できるのが大きな魅力です。詳しくはこちら。
バーコードの種類(JAN、QRコードなど)
「バーコード」と一言で言っても、実はたくさんの種類があります。最も身近なのは、商品パッケージについている「JANコード」でしょう。13桁または8桁の数字で構成され、どの事業者のどの商品かを示す世界共通の識別子です。また、最近よく見かける四角いモザイク模様の「QRコード」もバーコードの一種(二次元コード)です。JANコードが数字しか扱えないのに対し、QRコードは数字、英字、漢字など、より多くの情報を格納でき、URLを埋め込んでWebサイトへ誘導するといった使い方もできます。他にも、物流で使われる「ITFコード」や「CODE39」など、用途に応じて様々な種類が使い分けられています。
近未来技術?「RFID」の仕組み
RFIDの仕組みと通信方法
RFIDは、Radio Frequency Identificationの略で、電波(無線通信)を使って情報をやり取りする技術です。仕組みは、情報を記憶する「ICタグ(RFタグ)」と、その情報を読み書きする「リーダ/ライタ」の2つで構成されます。リーダ/ライタから発信された電波がICタグに届くと、タグがそれをエネルギーにして内部の情報を電波で返信します。この電波をリーダ/ライタが受信することで、情報を読み取るのです。バーコードのように一つ一つスキャンする必要がなく、リーダ/ライタの電波が届く範囲にあれば、複数のタグを一瞬で読み取れるのが最大の特徴です。
RFIDタグの種類(パッシブ、アクティブ)
RFIDのICタグには、大きく分けて「パッシブタイプ」と「アクティブタイプ」の2種類があります。パッシブタイプは、タグ自体に電池を内蔵しておらず、リーダ/ライタからの電波をエネルギー源として動作します。そのため、小型で安価、半永久的に使えるのがメリットですが、通信できる距離は数cmから数m程度と比較的短めです。一方、アクティブタイプはタグに電池を内蔵しており、自ら電波を発信します。通信距離が数十mと長く、移動しているモノの管理にも向いていますが、その分サイズが大きく、価格も高くなり、定期的な電池交換が必要になるという側面もあります。
一目でわかる!バーコードとRFIDの比較表
| 項目 | バーコード | RFID |
|---|---|---|
| 読み取り方法 | 光学式(1対1) | 無線通信(複数一括) |
| 読み取り距離 | 短い(接触・近距離) | 長い(非接触) |
| 障害物の影響 | 受けやすい(見えないと読めない) | 受けにくい(箱越しでも読める) |
| 情報量 | 少ない | 多い |
| 情報の書き換え | 不可 | 可能 |
| コスト | 安価 | 比較的高価 |
| 汚れ・破損 | 弱い(かすれると読めない) | 比較的強い |
この表を見ると、両者の違いがはっきりしますね。バーコードは手軽で低コストなのが強みですが、読み取りに手間がかかるという弱点があります。一方、RFIDはコストはかかりますが、一括読み取りや障害物への強さなど、バーコードの弱点を克服する多くのメリットを持っています。どちらが良い・悪いではなく、それぞれの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが重要です。
メリット・デメリットを徹底比較!どっちを選ぶ?
バーコード活用のメリット・デメリット
バーコードの強み:低コストと手軽さ
バーコードの最大のメリットは、何と言っても導入コストの安さと手軽さです。バーコード自体はラベルに印刷するだけなので、1枚あたりの単価は1円以下と非常に安価。読み取り用のバーコードリーダも、数千円から手に入るものがあります。また、技術として広く普及しているため、関連するシステムやノウハウが豊富にあり、導入のハードルが低いのも魅力です。商品管理や在庫管理を手作業で行っている場合、まずはバーコードを導入するだけで、入力ミスが劇的に減り、作業効率が格段にアップします。スモールスタートで業務改善を始めたい場合に、最適な選択肢と言えるでしょう。
バーコードの弱点:読み取りの手間と限界
手軽なバーコードですが、弱点も存在します。それは、一つ一つをリーダでスキャンする必要があるため、大量の物品を処理するには時間がかかるという点です。棚卸し作業などで、何百、何千という商品を一つずつ「ピッ、ピッ」と読み取るのは、かなりの労力ですよね。また、バーコードはリーダの光を直接当てる必要があるため、ラベルが箱の奥にあったり、ビニールで覆われていたりすると読み取れません。さらに、ラベルが汚れたり、印字がかすれたりすると読み取り精度が落ちてしまうのもデメリット。情報の書き換えができないため、ステータス管理などには向いていないという限界もあります。
RFID活用のメリット・デメリット
RFIDの強み:一括読み取りと書き換え可能
RFIDの最大の強みは、なんといっても「一括読み取り」ができることです。例えば、RFIDタグが付いた商品が数十個入った段ボール箱があっても、箱を開けずに外からリーダをかざすだけで、中にあるすべての商品の情報を一瞬で読み取れます。これにより、棚卸しや検品作業の時間が劇的に短縮されます。また、タグに記憶されている情報を後から書き換えることも可能です。例えば、製造工程の進捗状況をタグに書き込んでいけば、リアルタイムでの進捗管理が実現できます。バーコードでは難しかった「個品管理」や「ステータス管理」を容易に行えるのが、RFIDの大きな魅力です。
※条件によっては一括読み取りで、一部のRFIDタグ同士による干渉などで読み取れない場合があることに注意して下さい。
RFIDの弱点:コストと電波干渉のリスク
多くのメリットを持つRFIDですが、導入にはいくつかのハードルがあります。まず、コストの問題です。ICタグの単価は安いものでも1枚数円から数十円、リーダ/ライタも数万円から数十万円と、バーコードに比べて高価です。管理したいモノの数が多ければ多いほど、初期投資は大きくなります。また、RFIDは電波を使うため、水や金属の影響を受けて読み取り精度が落ちることがあります。これを電波干渉と呼びます。例えば、金属製の棚に商品を置いたり、液体が入った容器にタグを貼ったりすると、うまく読み取れないケースがあるのです。導入する際は、事前に現場環境でテストを行い、最適なタグやリーダを選ぶ必要があります。
どちらを選ぶべき?シーン別使い分けガイド
結局、バーコードとRFIDのどちらを選べば良いのでしょうか。答えは「目的と予算による」です。例えば、スーパーやコンビニのように、多種多様な商品を低コストで管理したい場合は、バーコードが最適です。一つ一つの商品をレジでスキャンする運用が確立されていますからね。一方で、アパレル店舗のように、大量の商品の棚卸しを短時間で終わらせたい、あるいは無人レジを導入したいといった場合には、RFIDがその真価を発揮します。また、工具やIT資産など、高価な備品の貸出管理や所在管理を行いたい場合も、情報の書き換えが可能で、個体を識別できるRFIDが向いています。自社の課題は何か、どんな業務を効率化したいのかを明確にすることが、最適なツールを選ぶ第一歩です。
事例で学ぶ!具体的な活用シーン
【在庫管理】バーコード活用でピッキングミスを削減
ハンディターミナルを使った入出荷検品
倉庫業務において、人的ミスが発生しやすいのが入出荷の検品作業です。伝票を目で見て、商品を目で見て確認する方法では、どうしても「数量の間違い」や「商品の取り違え」が起こりがち。そこで活躍するのが、バーコードとハンディターミナルです。入荷時には、商品のバーコードをスキャンし、仕入れデータと照合することで、間違いがあればその場でアラートが鳴るようにできます。出荷時も同様に、ピッキングリストに基づいて商品のバーコードをスキャンすれば、正しい商品を正しい数だけ集められているかを確認できます。これにより、経験の浅い作業員でも正確な作業が可能になり、誤出荷の防止と顧客満足度の向上に繋がります。
【資産管理】RFIDで備品の位置を瞬時に把握
社内PCや重要書類の管理方法
「あのパソコン、誰が使ってるんだっけ?」「あの重要書類、どこに保管したかな?」といった、社内の資産や備品の管理に頭を悩ませていませんか?こうした課題は、RFIDで解決できます。管理したいパソコンやファイルの一つ一つにRFIDタグを貼り付け、部屋の出入り口にゲート型のリーダを設置します。すると、誰がいつ、何を持ち出したか、あるいは返却したかが自動的に記録されるのです。棚卸しの際も、ハンディリーダを持って部屋を歩き回るだけで、そこにある資産のリストが一瞬で作成できます。探す手間が省けるだけでなく、資産の紛失や情報漏洩のリスクを低減させる効果も期待できます。
【店舗運営】RFID導入で無人レジ・万引き防止を実現
アパレル業界での成功事例
アパレル業界は、RFIDの活用が最も進んでいる分野の一つです。例えば、大手アパレルチェーンでは、全ての商品にRFIDタグを取り付け、セルフレジを導入しています。買い物客は、商品をレジ台の上に置くだけで、一瞬にして合計金額が計算され、会計を済ませることができます。レジ待ちの行列が解消されるだけでなく、店舗側もレジ作業の人員を削減できるというメリットがあります。また、別のRFIDタグを活用することで万引き防止も対応できます。会計が済んでいない商品が店の出口ゲートを通過すると、警報が鳴る仕組みになっているのです。在庫管理から会計、防犯までをRFIDで一元管理することで、劇的な業務効率化と新しい買い物体験を実現しています。
まとめ
今回は、バーコードとRFIDの基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、そして具体的な活用事例までを詳しく解説しました。バーコードは「低コストで手軽」、RFIDは「高機能で業務を劇的に効率化できる」という特徴があります。どちらか一方が優れているというわけではなく、自社の課題や予算、管理したいモノの特性に合わせて最適なツールを選ぶことが成功のカギです。この記事を参考に、あなたの会社の業務改善に繋がる一歩を踏み出してみてくださいね。本コラムでは、今後も皆様のお役に立つ情報の発信を続けてまいります。
投稿者プロフィール
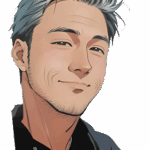
- 業界27年のベテラン営業マン兼ライター。
積極的に海外からも良い製品を探してくるが基本的にはモノづくり大好き人間。
投稿者の最新記事
 事例紹介2026.02.10【食品工場向け】HACCP対応はタブレットで記録!ペーパーレスで実現する衛生管理
事例紹介2026.02.10【食品工場向け】HACCP対応はタブレットで記録!ペーパーレスで実現する衛生管理 事例紹介2026.02.09【物流担当者必見】誤出荷を根絶するバーコード検品システムの仕組み
事例紹介2026.02.09【物流担当者必見】誤出荷を根絶するバーコード検品システムの仕組み 基礎知識2026.01.22【医療従事者向け】GS1バーコードの基礎知識とPMDA対応について詳しく解説!
基礎知識2026.01.22【医療従事者向け】GS1バーコードの基礎知識とPMDA対応について詳しく解説! 基礎知識2026.01.22【必読】医療安全管理者向け!3点照合システムとバーコード運用の基礎
基礎知識2026.01.22【必読】医療安全管理者向け!3点照合システムとバーコード運用の基礎

